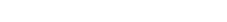第13回緑の教室 7月12日(土)甲府市の県立文学館にて開催
講師に富士山科学研究所の安田泰輔先生(理学博士)を迎え、気候変動で外来植物は増えるのか?について学びました。
まず初めに、特定外来生物に指定されるアレチウリの繁茂を事例として、河川敷で広がるとどうなるか?農耕地へ入るとどうなる?について、説明をうけました。次に琵琶湖では外来性の水草である、ナガエノツルノゲイトウやオオバナミズキンバイが大繁茂し、船の航行障害が発生したことなど、説明を受けました。対策しない場合には被害が発生し、かつ、駆除コストは増大になります。有効な対策をした場合、コストは低く済むと考えられ、対策の実現にはモニタリングが重要ということが分かりました。
そして、気温が1度上がると、植物に大きな影響を与えることなど、気候変動が進んだ場合、外来植物は増加すると予測される説明を聞きました。
また県内各地での取り組み、学校教育での取り組みも盛んに行われているようです。
自然観察することが、自然変化を知ることになるので、生き物好きを育てることが大事なのかもしれないと言うことを、先生から分かりやすく説明していただき、とても勉強になりました。


 ▶
▶ 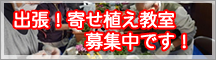

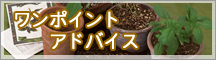



 ▶
▶