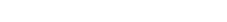第7回緑の教室 6月15日(日)富士川町民会館にて開催
講師に昆虫の多様性及び害虫について山梨県森林総合研究所の専門員として長年調査されております樹木医の大澤正嗣先生をお迎えし、病害虫について学びました。
初めに山梨県全域で被害が出ている病害虫について説明がありました。最大に被害が出ている病害虫は松くい虫(松材線虫病)であるとの事。
舌を噛みそうな名前のマツノマダラカミキリがマツノザイセンチュウを樹木の中に運び込み、カミキリ虫が産卵、繁殖し、最大でも1mmの線虫が弱った松の中で増殖し木は枯れてしまう。全国的に被害が出ているとのことでした。
次にキクイムシによるナラ枯れ(ブナ科樹木萎凋病)、こちらも小さなカシノナガキクイムシが木に穴を開けナラ菌を木の中に運び込み枯らしてしまうと、どちらの害虫も共生し繁殖していることをわかりやすく説明して頂きとても勉強になりました。
他にも問題となっている指定外来生物、外来種、カメムシ、アブラムシ他、多岐にわたり教えて頂きました。害虫の増加は、人間の生活スタイル、地球温暖化などによる自然環境の変化が影響している。長い年月をかけて今の状況にあるなど奥の深い学習会でした。
最後に、特定外来生物で説明があった、環境省指定のクビアカツヤカミキリは、見つけたら早期に駆除し被害を拡大させないことが重要であるり必ず知らせて欲しいとのことで学習会を終わりました。



 ▶
▶ 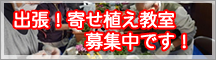

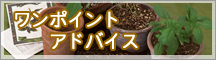



 ▶
▶